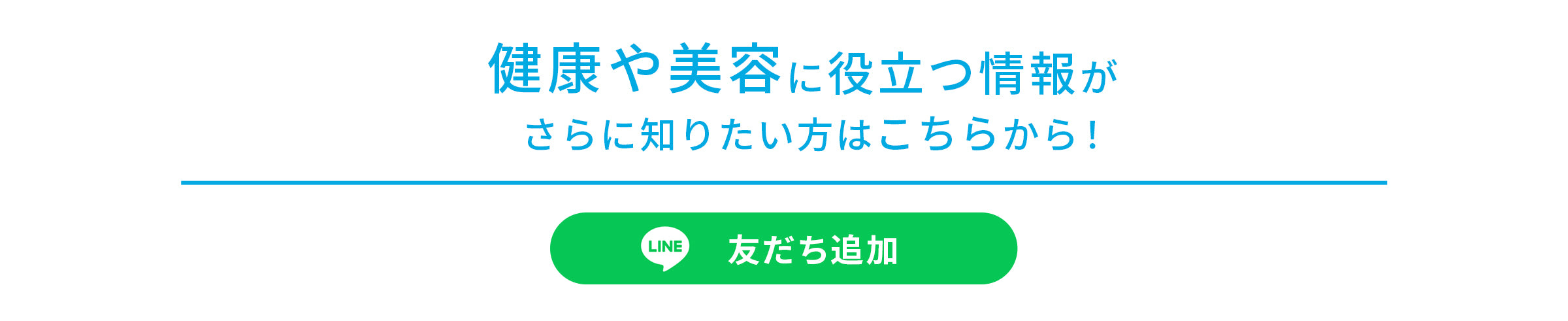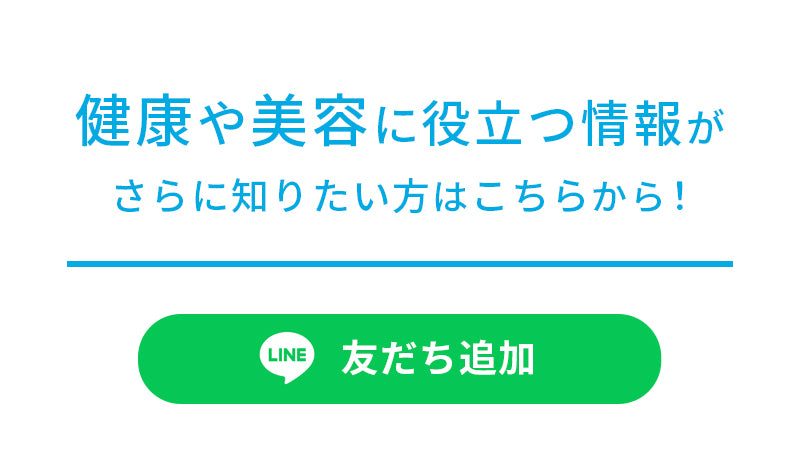離乳食完了期の進め方について
(生後12~18ヶ月)

離乳食完了期(生後12~18ヶ月:1歳~1歳6ヶ月)の進め方について、離乳食後期から移行するタイミングや与える食材の種類、味つけ、硬さ、大きさ、量などの調理のポイントや1日のスケジュールや献立をわかりやすく解説します。先輩パパやママの体験談も掲載中!
完了期(12~18ヶ月)の
スタートはいつから?
離乳食完了期では、形のある食べ物を噛みつぶすことができるようになります。必要なエネルギーや栄養素をほぼ母乳やミルク以外の食べ物から摂れるようになり、食事は1日3回と補食(おやつ)になります1)。
離乳食完了期を始める目安は12~18ヶ月ごろ(1歳~1歳6ヶ月)とされていますが、個人差があるため、赤ちゃんの様子をよく観察しながらそれぞれのペースで進めていくことが大切です1)。
離乳食完了期を迎える赤ちゃんの成長の目安2)
- 前歯が8本生えそろう(1歳前後)
- 歯を使うようになり、噛んだりかじったりが上手になる
- 前歯で一口量を噛み取れるようになる
- 手づかみ食べ中心からスプーンやフォークも使いたがるようになる
- 完了期後半ごろ、奥歯(第一乳臼歯)が生え始める
離乳や赤ちゃんの成長について心配なことがあれば、小児科の病院や保健センターの管理栄養士、保健師などに相談しましょう2)。
離乳食完了期の進め方
赤ちゃんの成長に応じて食事量や種類や形を調整し、噛んで食べる意欲を育てていくことが大事です。だんだんと生活リズムも整え、楽しく食べる経験を積み重ねていきましょう1)。
進め方のポイント1)2)3)
- 1日3食(朝・昼・夕)を習慣にし、家族の食事の仲間入りができるようにする
- 軟飯からごはんに移行する
- 歯ぐきで噛める食事を用意して噛む力を育てる
- 手づかみしやすいメニューを用意し、自分で食べる練習をする
- 補食(1日1~2回)は食事に影響しない範囲で与える
どんな食材を与えていいの? 味つけは?
離乳食完了期の栄養バランスは大切ですが、あまり難しく考えず、炭水化物、ビタミン・ミネラル、たんぱく質を組み合わせていけば大丈夫です2)。
6ヶ月以降は鉄分が不足しやすいので、鉄を多く含む食品(大豆製品、ほうれん草、牛肉、卵、まぐろ、青背の魚、小松菜、豚肉、レバーなど)を取り入れたメニューづくりをします2)。
また、味つけについては薄味(食塩濃度0.5%以下)を心がけることが大切です3)。
気をつけたいポイント2)
- 味つけに香辛料を使ったり、加熱しない牛乳を飲んだりするのは1歳になってからにする
- はちみつは満1歳までは与えない
- 離乳食完了期に入っても避けたほうがいい食材:肉・魚・卵の生もの、カフェインを含むもの、のどにつまりやすいもの1)2)3)
硬さや大きさ、量の目安はどれくらい?1)2)
この時期の赤ちゃんは、前歯が生えそろって、奥歯が生え始めますが、まだ噛む力は強くないので、歯ぐきで噛める肉団子程度の硬さを目安とします。大きさは、手づかみできるくらいにして、量の目安は以下の表通りです。赤ちゃんの成長には個人差がありますので、表はあくまで目安として考えてください。
| 区分 | 1回の量1) | 目安量※4) | 調理形態の目安 〈歯ぐきで噛める硬さ〉 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 穀類 | ごはん | 軟飯90~ ごはん80g |
軟飯子ども 茶碗1杯~ ごはん子ども 茶碗2/3杯 |
歯ぐきで噛める硬さ |
| 食パン | 30g | 8枚切り・ 2/3枚4) |
トーストを小さくちぎる | ||
| うどん | 乾麺30g、 ゆで麺90g4) |
3/5束 | 長さは2cm~5cm | ||
| Ⅱ | 野菜・くだもの | にんじん | 40~50g | 1/4本 (40g) |
1cm角からひと口大へ |
| トマト | 40~50g | 1/2個 (皮と種を除く) (40g) |
|||
| キャベツ | 40~50g | 葉4枚 (40g) |
|||
| ほうれん草 | 40~50g | 2~3株 (40g) |
|||
| 小松菜 | 40~50g | 葉先12枚 (40g) |
|||
| ブロッコリー | 40~50g | 小房2と 2/3個 (40g) |
|||
| Ⅲ | 魚 | 白身魚 | 15~20g | さしみ2切れ | 粗ほぐし |
| ツナ缶 (水煮) |
15~20g | 大さじ 1.5弱~ 大さじ2弱 |
|||
| 肉 | 鶏ささみ | 15~20g | 1/3本強 | ひき肉・うす切りを刻む | |
| ひき肉 | 15~20g | 大さじ1~ 大さじ1強 |
|||
| レバーペースト | 15~20g | 大さじ1~ 大さじ1強 |
|||
| 豆腐 | 豆腐 | 50~55g | 約1/6丁 | 2~3cm角 | |
| 卵 | 卵 | 30g~40g | 全卵1/2~ 2/3個 |
オムレツ、卵焼き、目玉焼きなど | |
| 乳製品 | 乳製品 | 100g | - | チーズは1~2cmの塊 | |
※1回の食事あたりの目安量です。同じ区分の食材を複数与える場合は、食材1つあたりの量を減らすなどして対応します
離乳食とミルクのバランス
離乳の完了とは、母乳やミルク以外の食べ物からエネルギーや栄養素がほぼ摂取できるようになった状態を指しますが、それは母乳や育児用ミルクを一切飲んではいない状態というわけではありません1)。
母乳は欲しがるだけ、育児用ミルクは食欲や成長に応じた量を、補食のときや就寝時にあげましょう2)3)。
1日のスケジュール
離乳食完了期では1日3回の食事が定着してきます。生活のリズムを整えるために、朝食を取ることが大切です。この頃はまだ1回の食事で多くの量を食べることができないため、食事の合間に捕食(おやつ)をあげて、エネルギーや栄養を補うようにしましょう4)。捕食(おやつ)は、ごはんやパン、いも類などを中心に、くだものや牛乳、野菜、小魚などを組み合わせます。
|
|
離乳初期 〜1日のスケジュールの目安〜 |
|---|---|
| 7:00~ 8:00頃 |
|
| 10:00頃 |
|
| 12:00頃 |
|
| 15:00頃 |
|
| 18:00頃 |
|
先輩ママの体験談
Voice

小さいときは何でも食べていたが、完了期になるとだんだん好き嫌いが出てきて、特に緑色の野菜を嫌がるようになった。心配だったが、無理に食べさせようとせず他の色の野菜をあげるようにしていた。5歳になった今では「一口だけ頑張ってみよう」という声かけで、緑色の野菜も少しずつ食べてくれるようになっている。(現在5歳の男の子)
Voice

2つ上のお姉ちゃんと同じものを食べたがっていた。まだこの月齢ではあまり与えたくない食材・味つけのものを特に食べたがっていたので、同じものはあげないようにしつつ、なるべくお姉ちゃんのごはんと見た目を近づけるようにすると、たくさん食べてくれた。(現在3歳の女の子)
離乳食を食べさせるときのコツ
最初は上手に食べられないことも多いかもしれませんが、あらかじめ準備をするなど工夫できるとよいでしょう2)3)。
食事の環境を整えるコツ2)
- 床にビニールシートを敷く、エプロンをつけるなどして食べこぼしに備える
- スプーンやフォークを使いたがったときにすぐに渡せるように用意しておく

離乳食を準備するときのコツ3)
- 離乳食は傷みやすいので、清潔に気をつけて調理し、すばやく食べさせる
- 適温で与える(熱すぎず、冷たすぎず)
- 離乳食づくりが負担にならないよう、電子レンジやフリージングを利用し、ベビーフードも上手に取り入れる。

食事の時間を楽しむコツ1)3)
- 「これは〇〇だよ、おいしいね」など、楽しくコミュニケーションをとりながら食べる
- 日中はコップで飲む練習をする

1日の献立例(朝・昼・夜)
離乳食完了期の具体的な献立例をご紹介します。食材の量も参考にしてください。
朝食

Cooking!
ロールサンドイッチ
- 材料(1人分)
-
- パン(耳は除く):8枚切り1枚
- バナナ(ペーストにつぶす):2g
- プチトマト(湯剥きしてうす切り):5g
- ※出来上がったロールサンドは1cm幅くらいに食べやすく切って盛り付けます。
ホットミルク
- 材料(1人分)
-
- 牛乳:90cc
ツナと野菜のオムレツ
- 材料(1人分)
-
- 玉ねぎ(レンジで軟らかく加熱しておく):10g
- にんじん(レンジで軟らかく加熱しておく):5g
- ピーマン(レンジで軟らかく加熱しておく):5g
- 溶き卵:1/2個分
- ツナ(油不使用):5g
- オリーブ油:少々
昼食

Cooking!
けんちんうどん
- 材料(1人分)
-
- うどん:80g
- 大根:15g
- にんじん:5g
- ほうれん草:5g
- 絹ごし豆腐:50g
- だし汁:150cc
- みりん:小さじ2/3
- しょうゆ:小さじ2/3
フルーツ
- 材料(1人分)
-
- ぶどう(皮をむいて1個を4等分に切る):25g
夕食

Cooking!
白菜と豚肉のミルフィーユ
- 材料(1人分)
-
- 白菜:20g
- 豚ひき肉:20g
- 片栗粉:ひとつまみ
- だし汁:50g
- 塩:少々
ジャガイモのガレット
- 材料(1人分)
-
- じゃがいも:15g
- 小麦粉:3g
- 粉チーズ:少々
- 油:少々
ごはん
- 材料(1人分)
-
- 軟飯~ご飯:80g
おかか和え
- 材料(1人分)
-
- にんじん:15g
- だし汁:50g
- 鰹節:少々
Point
離乳食完了期はパパやママと同じものを食べる楽しみを発見できる時期です。先輩たちの体験談も参考に、あせらずゆったりとした気持ちで進められるとよいでしょう。